「肩こりがひどくて、頭痛もある・・」
「腰がそろそろピキッといきそう・・」
「デスクワークで目がつらい・・」
このようなつらいコリには全身のマッサージがオススメです。
呼吸しやすく、全身ゆるめるマッサージ
i-BALANCEは強いマッサージや、バキバキするような矯正は行いません。
筋肉の走行や関節の動き、つらさの原因となる部分を考え、全体的に調整していきます。
デスクワークなどで丸まった体を整えて肋骨が動きやすい状態へ導くため、呼吸がしやすくなり、全身のめぐりが良くなります。
猫背や反り腰などの不良姿勢も自然と解消されていくため、定期的なメンテナンスにもオススメなメニューです。
痛みや痺れがある場合は鍼灸も可能
痛みや痺れなど症状がつらい場合には、鍼灸を提案させていただきます。
髪の毛ほどの細い針を使い、原因となる筋肉へアプローチ。
さらに微弱な電気を流すことでコリを解消し、痛みを緩和させていきます。
恐怖心がある場合には無理には行いませんが、やってみるとほとんどの方が「大丈夫、むしろ気持ちよかった」という感想をお持ちになります。
この機会にぜひ、お試しください。
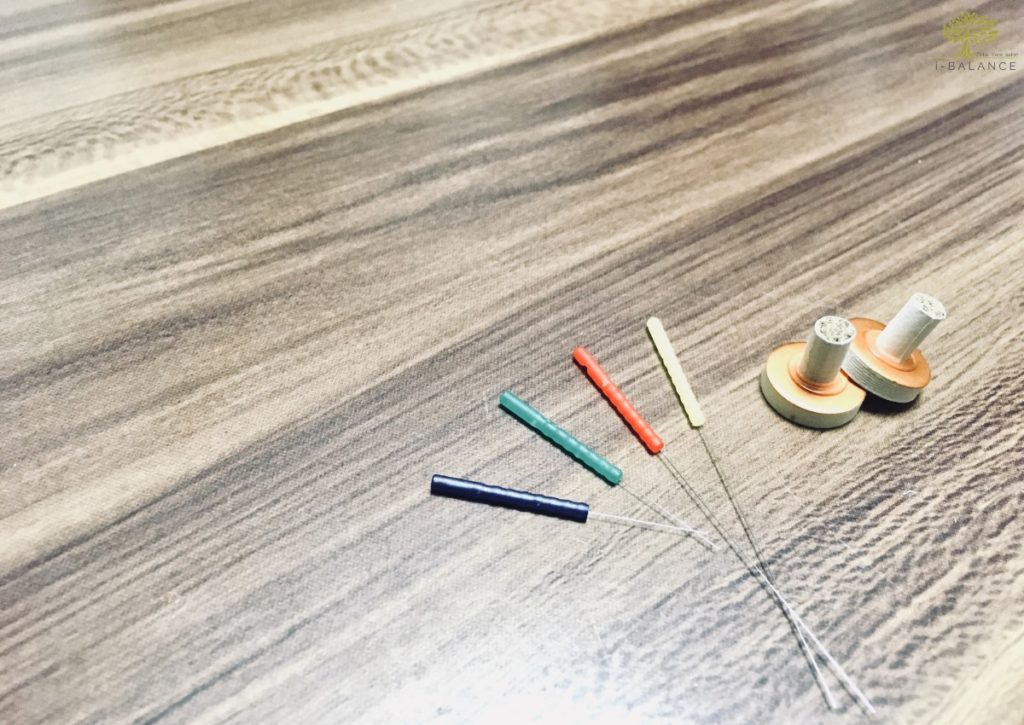
リフレクソロジーで足の疲れもケア
足のお疲れやむくみも気になる方には頭と体と足ツボマッサージもおすすめ。
じんわりと温かいホットジェルを使用したリフレクソロジーで、足裏から膝上までしっかりケアしていきます。
温めながらのマッサージで心もケア
黄土ホットパッドや遠赤外線温熱器、ヒートマットを使用し、マッサージによる血流促進効果をさらに高めて施術を行います。
足、腰、お腹、目元を温めるため施術後は体がぽかぽかです。
温めながらのマッサージと鍼灸で、呼吸のしやすい楽な体を取り戻しにいらしてください。

